久しぶりに見たくなったので、6時間近い作品ですがあっという間に見終わってしまいました。
私がユゴーのレ・ミゼラブルに出会ったのは学生時代のちょうど2004年です。岩波文庫で出ていましたが文字が小さく読みにくいなと思い、潮出版社から出ている単行本のユゴー文学館を奮発して購入した記憶があります。本一冊で定価5000円は学生時代の当時はとても高かった!でも今でもずっと大切な本です。2004年にNHKで4夜連続放送していたのを見ていた人は多いのではないでしょうか。当時はビデオテープで録画していました(笑)
その後数十年してミュージカルで上演され、有名になりましたが、ちょっと待ってください!
ミュージカルの前に、TVシリーズ完全版を見て欲しいし、さらに言うならば、原作の本を読んでほしい!
再び映画を見てみると、当時見えていなかったところが見えるようになった気がします。よりキリスト教的な要素を感じ取れるようになったといいますか。
ユゴーは何を見ていたのか。言語化がむずかしいけれども、私なりに思うところは精神科医スコット・ペックさんの以下の言葉です。
精神科医のモーガン・スコット・ペック『The Road Less Traveled』住く人の少ない道:から引用したいと思います。
精神的成長が労の多い困難な過程であることは、何度も強調した。これはそれが自然の抵抗、物事をあるがままに保ち、ことを行うのに古い地図古いやり方に固執し、易きにつく自然な傾向に逆らっているからである。われわれの精神生活に働くエントロピーの力、この自然な抵抗、精神生活に働くエントロピーの力について、さらに手短かに述べなければならない。身体的進化の場合と同じく、この抵抗が克服されるのが奇跡なのである。われわれは成長する。そのプロセスに抵抗するすべてに逆らい、われわれはよりよい人間になる。みんなというわけではない。やさしくもない。しかしかなりの人が、何とか自分自身とその教養とを高めてゆく。どういうわけかより困難な道を選び、われわれを生まれ落ちた泥沼から這いあがるよう、促す力があるのである。
精神的進化のこの図式が個々人の存在にあてはまる。各人には成長へのおのずからの促しがある。この促しを働かして独力で自らの自然の力と戦わねばならない。この図式は人類一般にもあてはまる。われわれが個人として進化するにつれて、社会の進化が促される。子ども時代にわれわれを育ててくれた文化は、成人したわれわれのリーダーシップによって育てられる。成長をなしとげた者はその果実を楽しむだけでなく、世界に同じ果実をもたらす。個人として進化することで、われわれは人間性を担う。そして人間性が進化するのである。・・・
それにしても、個人としてかつ種としてのわれわれに、内なる無気力という自然な抵抗に逆らって成長することを促す、この力は何なのか。すでに名はつけてある。それが愛である。愛は「自分自身と他者の精神的成長を養うため、おのれを広げようとする意思」として定義されてきた。われわれが成長するのはそのために努力するからであり、努力するのは自分を愛するからである。われわれが自分を向上させるのは愛によってである。他者が向上するのを助けるのは、他者を愛することを通してである。愛すること、おのれを広げてゆくことこそ、進化の行為である。それはまさに進みつつある進化なのである。あらゆる生命体に存在する進化の力は、人間においては愛として顕れる。人間の本性のなかで、愛はエントロピーの自然な法則にあらがう奇跡の力なのである。
『愛すること、生きること』スコット・ペック 創元社 「恩寵」 p283
単純にキリスト教的な博愛とか仏教などの慈悲という言葉で片づけてしまうと、地に足がついていないような浮遊感がただよってしまう気がします。精神科医の先生が語る「愛」はすこし重みが違うなと。頑張って言葉をひねり出す試み、そういった「共に」「知る」こと目指す良心(conscientia)の力を信じたいと思います。
人間的可能性をもつひとりの人への無条件の肯定的な眼差し。共に精神的成長にあり、共に未来へ歩む仲間たる信じる心。御心に適う人にあれ。
映画の最後、光とともに目を閉じるジャン・バルジャン。そのとき、J.S.バッハのカンタータ BWV 132「Bereitet die Wege, bereitet die Bahn」(道を備え、大路を備えよ)が頭をよぎりました。
第6コラール
Ertöt uns durch deine Güte;
Erweck uns durch deine Gnad;
Denalten Menschen kränke,
Dass der neu’ leben mag
Wohl hie auf dieser Erden,
Den Sinn und Begehrden
Und G’danken habn zu dir.
Cantata BWV 191
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
「いと高きところには、栄光、神にあれ。地には平和、御心に適う人にあれ。」ルカによる福音書2章14節
「神は愛です。愛の内にとどまる人は、神の内にとどまり、神もその人の内にとどまってくださいます。」ヨハネ 第一の手紙4・16
ミリエル司教の燭台とその蝋燭の光は今も人々を照らしていることでしょう。
哲学堂書店 浦山幹生
古本の買取はお任せください。哲学書・学術書・洋書 買取強化実施中
古本 買取・処分 承ります。まずはお問い合わせください。
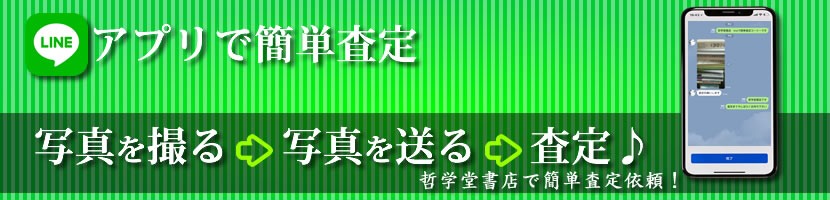
これから古書・古本買取の売却・買取をご検討中のお客様、Lineアプリ査定がおすすめLineアプリで簡単査定はこちら
これから哲学書・思想書の古書・古本買取の売却・買取をご検討中のお客様、ぜひ当店の買取サービスをご利用してみてください。買取依頼はこちら
これから学術書・専門書の古書、古本の売却・買取をご検討のお客様、ぜひ当店の買取サービスをご利用してみてください。買取依頼はこちら
これから原書・洋書の古書、古本の売却・買取をご検討のお客様、ぜひ当店の買取サービスをご利用してみてください。買取依頼はこちら
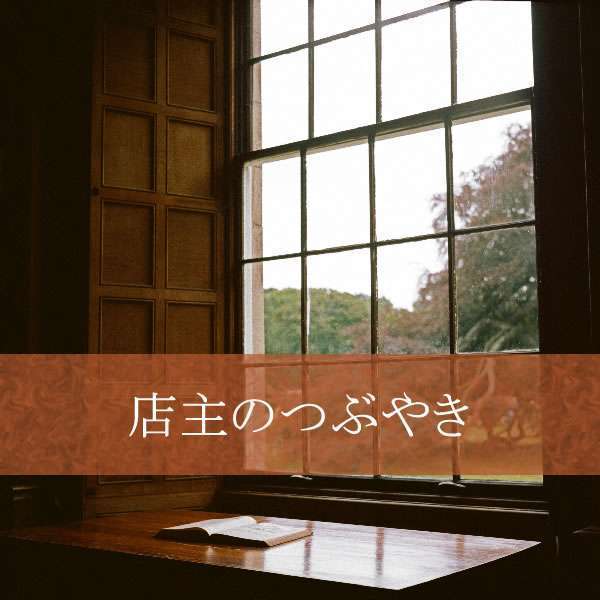






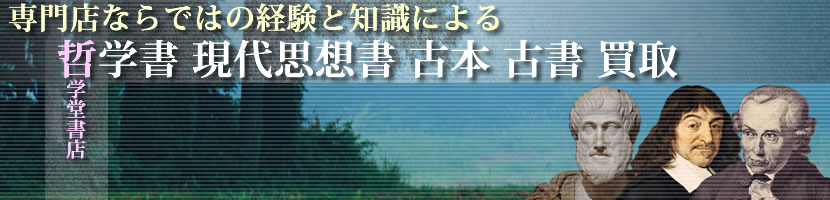


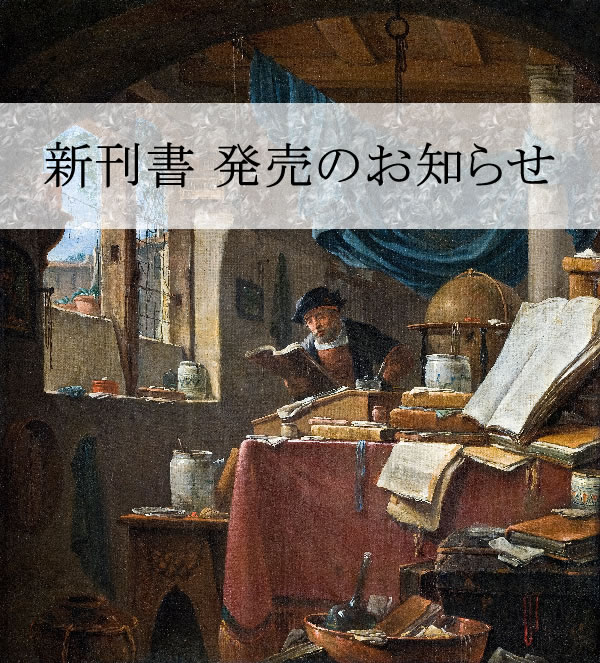

コメント